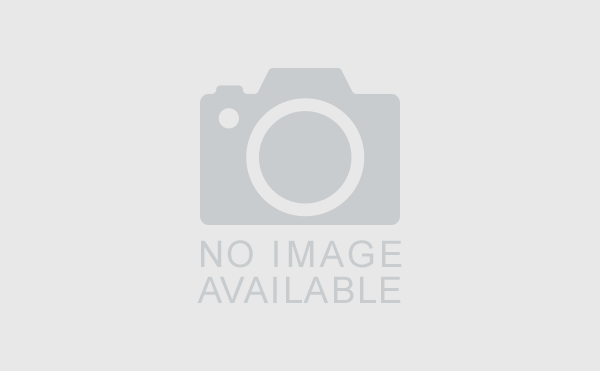面会交流とは?──別居親の思いと同居親の現実、その間にある“子の利益”を考える
離婚後、子どもと別れて暮らす別居親が「子どもに会いたい」と願うのは自然なことです。
しかし、面会交流は別居親の当然の権利ではありません。
家庭裁判所の判断基準は一貫して、子どもの福祉にかなうかどうかにあります。
1.面会交流とは何か
民法766条では、父母が協議離婚する際に、面会交流の取り決めを行うこととされています。
これは、子どもが両親と適切な関係を保つことを目的とした制度です。
ただし、「会いたいから会わせる」という一面的な考えではうまくいきません。
面会交流の可否や方法は、子どもの生活や感情に与える影響を十分に踏まえて判断されます。
2.なぜ面会交流が争われるのか
面会交流は、実務上でも最も対立が激しくなりやすいテーマの一つです。
別居親が会いたいと願う一方で、同居親が会わせたくないと考えるケースは少なくありません。
よくある背景として、以下のような事情があります。
- 過去にDVやモラハラがあった
- 子どもが混乱し情緒不安定になることを心配している
- 親同士の信頼関係が完全に崩壊している
- 再婚相手や新しい家族との関係に悪影響がある
3.家庭裁判所での調整の進め方
家庭裁判所では、まず面会交流調停が行われます。
話し合いがまとまらなければ、審判へと移行し、家裁調査官が子どもや家庭の状況を調査します。
最近では、まず「試行的面会」を行い、段階的に内容を調整していく方法も採られています。
4.面会の頻度は「月1回程度」が多数
実務上、面会交流は月1回程度で合意されるケースが圧倒的に多いです。
これは同居親が無理なく継続できる現実的なラインとして定着しています。
一方で、別居親からは「少なすぎる」という不満も強く、調整には慎重な配慮が求められます。
まずは継続可能な範囲から始め、信頼関係の構築を経て内容を見直すというアプローチが現実的です。
5.子どもが面会を拒否している場合
「子どもが嫌がっている」という理由で、同居親が面会を拒否することも少なくありません。
このような場合、子どもの意思は尊重される一方で、その背景や影響要因についても丁寧に検討する必要があります。
場合によっては、別居親との関係再構築に向けた心理的支援や段階的な働きかけが重要になることもあります。
6.面会交流の本質──子の利益と親の気持ちのバランス
面会交流は別居親の権利と見られがちですが、実際には子どもの安心・安全を守ることが最優先です。
家庭裁判所も常に「この面会は子どもにとって有益か」という視点で判断を行います。
とはいえ、別居親の思いも軽視されるべきではありません。
子どもと再び穏やかな関係を築くために、どのような方法が可能かを、当事者双方が冷静に模索していくことが必要です。
まとめ──子どもの未来を見据えて
面会交流は感情的な対立を引き起こしやすいテーマです。
しかし最終的に重視すべきは、子どもの心が安定し、安心できる環境で成長できるかどうかという点です。
法律の知識だけでは解決できない部分も多くありますが、現実的な解決策をともに考え、実行していくことが可能です。
どうぞお気軽にご相談ください。
📍おさち法律事務所
長野県岡谷市長地柴宮3-17-5 FKビル東204