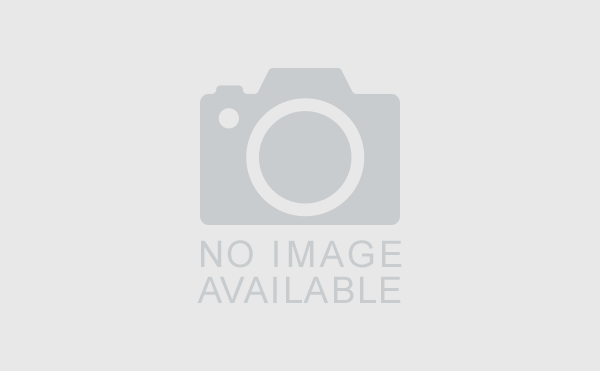逸失利益の終期は67歳?──高齢化社会の中で立ち止まって考える
交通事故などで後遺障害が残った場合、逸失利益(将来の収入減少に対する補償)が問題になります。
その算定において重要なのが「喪失期間」=いつまで減収が続くと考えるかという点です。
ここには「原則」と「例外」が存在しますが、最近ではその“原則”そのものに再考の必要があるのでは?という声も上がっています。
【原則】67歳までが終期
現在の実務では、就労可能年齢の上限を「67歳」とするのが原則です。
被害者が若年〜中年層の場合、逸失利益は症状固定日から67歳までの期間で算定されます。
これは、統計的に多くの人が65歳〜70歳までに退職・就労終了していることに基づいた慣行です。
【例外】高齢者は「余命年数の半分」
被害者がすでに高齢(おおむね60歳以上)の場合、67歳までではなく「平均余命の半分」を労働能力喪失期間とするのが定着しています。
これは「高齢者の働く可能性が年齢とともに低くなる」ことを前提とした、あくまで簡便的なルールです。
【問題提起】本当に「67歳」でいいのか?
日本はすでに高齢化社会──いや、超高齢社会に突入しています。
定年は65歳が標準となり、70歳就業法の施行により、企業には70歳までの雇用確保努力義務も課されました。
実際、70歳以上でも元気に働く人は年々増えています。
それにもかかわらず、逸失利益の終期は今も「67歳」が“画一的な終点”として扱われている──
このギャップに、時代遅れの気配を感じないでしょうか?
実際の運用:柔軟な判断も可能
もちろん、実務においても「67歳以降も就労を継続する予定があった」「雇用契約が延長されていた」など、個別事情により終期を延長する主張は可能です。
しかし、現実としては“67歳原則”が強く機能しており、証拠がなければ通らないことが多いのが実情です。
まとめ:変わる社会、変わらぬ基準
制度は安定性が必要です。
しかし、現実とズレすぎた基準が人の人生を適切に評価できるか?── この問いには、常に立ち止まって向き合う必要があると私は思います。
もし、事故さえなければ70歳まで働くことができたのに── そういう現実に対して「制度だから67歳までです」と切り捨ててよいのか。 それを考え直す時期に来ているのではないでしょうか。
📍おさち法律事務所|鳥川秀司 弁護士
長野県岡谷市長地柴宮3-17-5 FKビル東204
📞 初回相談無料