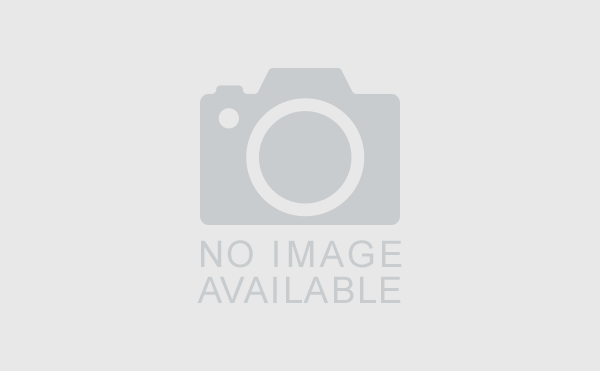後遺障害逸失利益における「年収」の考え方──原則と例外を押さえる!
交通事故で後遺障害が残った場合、逸失利益(将来の減収に対する損害)が認められることがあります。
この逸失利益を計算するうえで最も重要な要素の一つが「年収」です。
ただし、この「年収」の捉え方には原則と例外があり、実務ではその判断が大きな争点になることもあります。
ここではその基本的な考え方を整理します。
【原則】事故前年の実収入を基準にする
逸失利益の算定における基本原則は、事故前の現実の年収(実収入)を用いることです。
源泉徴収票、確定申告書、給与明細などから把握できる収入をベースにするのが原則です。
この方法は最も客観的で立証しやすく、保険会社との交渉や裁判でも広く使われています。
【例外】実収入がない・不安定な場合は「統計的収入」を使う
しかし、以下のような場合には、実収入を基準にするのが適切でないとされ、賃金センサス(厚労省の統計)が用いられます。
- 若年者(学生):学歴に応じた全年齢平均で算定(高卒・大卒で金額が異なる)
- 主婦(専業):女性の全年齢平均賃金を基準とする(家事労働の経済的価値)
- 自営業者:過去数年の申告収入の平均や実態調査に基づく補正が行われることも
- 高齢者:実際の就労状況や継続就労の意思能力により評価
- 障害者・無職者:就労支援実績や生活状況によって柔軟に判断される
実務では、これらのケースでもできるだけ具体的な就労実態・証拠を添えて主張することが重要です。
【最近の動き】障害者の想定年収をどう評価するか
最近の裁判例では、障害を理由に健常者よりも低い賃金センサスを適用することが「不当な差別にあたる」と判断された例も出ています。
これは、逸失利益の年収算定において「属性」だけではなく「可能性・支援の有無」も加味すべきという考え方で、今後の判断基準に影響を与える可能性があります。
まとめ:制度はある、でも実情も大事
逸失利益の年収算定は、原則として実収入に基づきます。
しかし、現実には働き方や人生設計は人それぞれであり、例外的な対応が求められる場面も多いのです。
保険会社の提示が「一律な統計基準」になっている場合、実態に合った主張を丁寧に積み重ねていくことが、正当な賠償を得るためには欠かせません。
📍おさち法律事務所|鳥川秀司 弁護士
長野県岡谷市長地柴宮3-17-5 FKビル東204
📞 初回相談無料