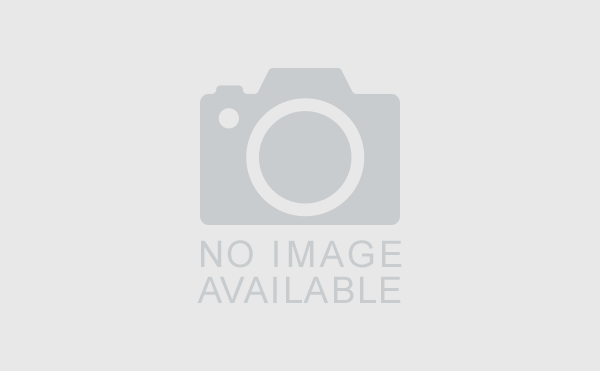後遺障害と労働能力喪失率──等級で決まる“現実”と、それでも見逃せない“個別の人生”
交通事故で後遺障害が残った場合、「逸失利益」を請求することができます。
ここで重要になるのが「労働能力喪失率」という考え方です。
しかしこの喪失率、実際には後遺障害の等級によって機械的に決まってしまうことが多く、本当にそれでいいのか?という疑問が残ります。
1.労働能力喪失率とは?
後遺障害によって、どの程度「働く力」が減ったかを数値で示したものです。
例えば、喪失率が35%であれば、収入の35%分の損失が続く、と考えて計算します。
2.等級でほぼ決まるのが現実
実務では、後遺障害の等級に応じて、労働能力喪失率が定型的に決められています。
以下がその目安とされている一覧です。
| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
|---|---|
| 1級 | 100% |
| 2級 | 100% |
| 3級 | 100% |
| 4級 | 92% |
| 5級 | 79% |
| 6級 | 67% |
| 7級 | 56% |
| 8級 | 45% |
| 9級 | 35% |
| 10級 | 27% |
| 11級 | 20% |
| 12級 | 14% |
| 13級 | 9% |
| 14級 | 5% |
これらはあくまで「目安」ですが、ほとんどの裁判でもこの基準通りに判断されるのが実情です。
3.定型化が助けになることもある
等級と喪失率がセットになっていることで、交渉や裁判での見通しが立てやすいというメリットもあります。
また、感情論ではなく数値で話ができるため、紛争の長期化を避けやすいという利点もあります。
4.でも…人の人生はそれぞれだ
同じ等級でも、誰にどんな影響があるかは大きく異なります。
たとえば:
- スポーツインストラクターが膝を痛めた12級
- 指先を細かく使う技術職の13級
このように、喪失率だけで本当の損害が反映されているかは疑問が残ります。
5.理想:個別事情をどう反映させるか
実務でも、特殊な職業や明確な影響がある場合には、喪失率を加算・調整する裁判例も存在します。
しかし、それを主張・立証するためには、具体的な資料・証言などが必要
「等級だけで判断するのはおかしい」と感じたら、その声をきちんと届ける準備が重要です。
6.まとめ:定型を知り、個別を忘れない
後遺障害等級ごとの喪失率は、一定の合理性と利便性があります。
しかし、すべての人に完全にフィットするものではありません。
だからこそ、「この基準でいいのか?」という問題意識を持ち、必要な場合はしっかりと個別事情を伝えることが大切です。
📍おさち法律事務所
長野県岡谷市長地柴宮3-17-5 FKビル東204
📞 初回相談無料